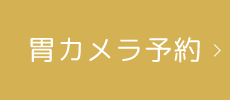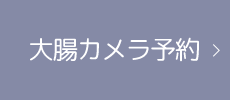ご来院の際は事前にWEBにて予約・問診の入力にご協力をお願いします。
ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。
C型肝炎とは
 C型肝炎ウイルスの感染経路は血液感染です。
C型肝炎ウイルスの感染経路は血液感染です。
日常生活で血液に直接触れることはあまりありませんが、
過去の輸血や血液製剤、感染者との性交渉、刺青や覚せい剤の使用などがきっかけとなります。
また、確率は低いですが出産時の母子感染などもあります。
C型肝炎ウイルスに感染すると約70%の方が症状のない持続感染者(不顕性感染)となり、慢性肝炎・肝硬変・肝臓がんと進行していく可能性があります。
慢性肝炎の患者さんのうち、約40%の方が20年以上の長い経過で「肝硬変」に進行します。
肝硬変になると年に7%の頻度で肝臓がんの発生が起こると言われます。肝硬変になると初期は肝臓の働きが保たれて合併症に乏しい「代償性肝硬変」と言われる状態ですが、進行していくと肝臓の機能が低下し様々な合併症・症状を伴う「非代償性肝硬変」になります。
輸血などの血液製剤では、現在ではチェックが厳しいため感染は起こりませんが、1992年以前の輸血、1994年以前のフィブリノゲン製剤、1988年以前の血液凝固因子製剤では、ウイルスのチェックが不十分だった可能性があるため、その時期に該当する処置を受けた方は感染している可能性がないわけではありません。ただ処置後に1年以上たってHCVの検査をしていて、陰性であれば感染はしていないと言えます。
C型肝炎の症状
 C型肝炎の経過はほとんどが慢性肝炎のため、急性肝炎のような激しい自覚症状がなく、気づかないうちに進行しているケースが多いです。しかし徐々に慢性化していくので、高い確率で肝硬変や肝臓がんに進行します。そのため、早期発見・早期治療が重要です。
C型肝炎の経過はほとんどが慢性肝炎のため、急性肝炎のような激しい自覚症状がなく、気づかないうちに進行しているケースが多いです。しかし徐々に慢性化していくので、高い確率で肝硬変や肝臓がんに進行します。そのため、早期発見・早期治療が重要です。
敢えて症状をあげるとすると、何となくだるい、疲れやすい、食欲がない程度の症状のためC型肝炎に特徴的な症状があるとは言えません。
病状が進行し、肝硬変や肝臓がんまで進むと、黄疸、体重減少、腹水、肝性脳症などの自覚症状がでてくる可能性があります。ただ症状が必ず出るわけではないので、健診などの際に肝硬変、肝臓がんが見つけるケースも散見されます。
C型肝炎の検査
血液検査・超音波検査を行います。
HCV抗体が陽性の場合は、HCV核酸増幅検査(HCV-RNA定量検査)を採血で行い、現在C型肝炎ウイルス持続感染しているかどうかを確認します。抗体検査では過去に治癒をしてウイルスのいない人でも陽性になってしまうからです。自然治癒も1割程度いるのではと言われています。
B型肝炎と同じように腹部エコー検査を実施し肝臓の状態を把握します。慢性肝炎や肝硬変、肝臓がんなどをチェックするうえで有効で、診断や経過観察にも使用できます。腹部エコー検査は簡便で、負担が少なく外来での実施が簡単なため、C型肝炎に限らず肝臓の疾患全般の経過観察にとても有効です。
またCT検査、MRI検査などの画像検査も肝臓がんの検索に有効です。
C型肝炎の治療
 薬物療法によってC型肝炎ウイルスを排除します。C型肝炎ウイルスはB型肝炎ウイルスと違い、完全排除ができる肝炎ウイルスです。
薬物療法によってC型肝炎ウイルスを排除します。C型肝炎ウイルスはB型肝炎ウイルスと違い、完全排除ができる肝炎ウイルスです。
そのためC型肝炎の治療はウイルスの排除と肝機能の悪化を防止することが目的となります。
以前はインターフェロンによる治療でしたが、現在は主にインターフェロンフリー療法があります。
C型肝炎ウイルスに対する治療薬は急速に進歩しており、治療の目標はウイルスを完全に排除することです。
C型肝炎の予防
変異が起こりやすいため、ワクチンの開発が極めて難しいです。
針刺し事故や注射器の使いまわしには注意しましょう。
注意点
C型肝炎ウイルスが排除されても、慢性肝炎・肝硬変によってついてしまった肝臓の傷はなくなりません。そのような傷跡から肝臓がんが発生します。
C型肝炎の治療が終わった後の肝臓がんのチェックを定期的に忘れずに行うことが大事です。