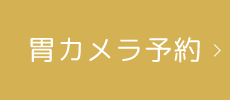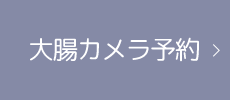ご来院の際は事前にWEBにて予約・問診の入力にご協力をお願いします。
ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。
予防接種とは
 予防接種とは、病原体(ウイルスや細菌)の感染を防ぐ効果が確認されたワクチンを接種することで、免疫のしくみを利用して、疾患に対する抵抗力を高める方法です。
予防接種とは、病原体(ウイルスや細菌)の感染を防ぐ効果が確認されたワクチンを接種することで、免疫のしくみを利用して、疾患に対する抵抗力を高める方法です。
予防接種によって、感染症を予防したり、感染症にかかった場合に重症化を抑えたりすることが期待されます。
予防接種の予約
 当院で予防接種をご希望の方はワクチンの準備が必要なため事前に予約が必要です。ご来院前にお電話でご予約をお願い致します。
当院で予防接種をご希望の方はワクチンの準備が必要なため事前に予約が必要です。ご来院前にお電話でご予約をお願い致します。
なお帯状疱疹ワクチンの予約はWeb予約で承っております。
予防接種を受ける際には「予診票」をよく読み、ご理解ください。
予防接種を受けられない方/
接種の際に注意が必要な方
- 発熱(37.5℃以上)がある方
- 重度の急性疾患をお持ちの方
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患等で治療を受けている方
- ワクチンに含まれる成分(鶏卵や安定剤など)にアレルギーがある方
- 接種後2日以内に発熱、発疹、じんましん等のアレルギー症状を起こした経験のある方
- けいれんを起こしたことがある方
- 免疫不全症と診断されたことがある、または先天性免疫不全症の血縁者をお持ちの方
※上記に該当する場合や、ご不安・ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
予防接種後の注意点
- 接種後10分程度は当院内、またはすぐに当院に戻れる場所にてお過ごしいただき、すぐに医師と連絡が取れる状態にしてください。
- 接種部位に異常反応がみられたり、体調に変化がみられたりする場合は、すぐに診察を受けてください。
- 体調変化の可能性があるため、接種後24時間は激しい運動や飲酒は避けてください。
- 接種部位は清潔に保ってください。
主な取扱ワクチン
インフルエンザワクチン
とは
インフルエンザは、インフルエンザウイルスへの感染によって起こります。症状としては、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、悪寒などの全身症状や、風邪に似た喉の痛み、鼻水、咳などがあります。小児や高齢者が重症化することもあります。小児では中耳炎を併発することが多く、けいれんを起こしたり、まれに急性脳炎を起こしたりすることもあります。高齢者や免疫力が低下している人は肺炎の合併症に注意が必要です。
毎年のワクチン接種
で予防
インフルエンザウイルスは毎年少しずつ特徴を変え、様々な型のインフルエンザウイルスが流行する厄介な感染症です。これに対応するためには、毎年のワクチン接種が必要です。
インフルエンザワクチン
の接種のタイミング
インフルエンザを予防する効果的な方法は、流行する前にワクチンを接種することです。接種後、効果が出るまでに2週間かかり、その効果は約5ヶ月持続するため、流行期に合わせて接種する必要があります。日本のインフルエンザ流行期は例年12月から翌年3月までなので、毎年10月下旬から12月までに接種すれば流行期に効果を出すことができます。
肺炎球菌ワクチン
肺炎とは
肺炎とは、肺が病原性微生物(主に細菌やウイルス)に感染して炎症を起こす疾患です。正常な状態では、呼吸器系の防御機能が働いて病原微生物を排除し、感染を防いでいます。しかし、何らかの原因で感染力が防御力を上回ると、病原微生物が上気道、下気道、肺に侵入し、感染症や肺炎を引き起こします。
加齢や疾患、ストレスなどで免疫力が低下すると感染しやすくなります。
肺炎にかかりやすく回復しにくい傾向にある高齢者や、慢性疾患のある方は特に注意が必要です。
肺炎球菌ワクチン
の接種による予防
肺炎の原因とされる菌はいくつかありますが、肺炎の原因として最も多いのは肺炎球菌で、成人の肺炎の20~40%を占めると考えられています。肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎やその他の感染症を予防し、重症化を防ぎます。ただし、すべての肺炎を予防できるわけではないので、接種後も肺炎にかからないように日常生活で注意する必要があります。
成人用肺炎球菌ワクチン
の接種が望まれる方
日本呼吸器学会が発表した「成人市中肺炎ガイドライン」(2007年)、「医療・介護関連肺炎ガイドライン」(2011年)に記載されている成人用肺炎球菌ワクチンの接種が推奨されるのは、以下の方々です。
- 65歳以上の方
- 養護老人ホームや介護老人保健施設などに居住されている方
- 慢性の持病がある方
(特に、COPDなどの呼吸器疾患、糖尿病、慢性心不全、肝炎や肝硬変などの慢性肝疾患) - 疾患や免疫抑制療法のため感染症に罹りやすい状態にある方
- 脾臓摘出などで脾臓機能不全がある方
高齢者を対象とした
定期接種
平成26年(2014年)10月より、高齢者を対象とした成人用肺炎球菌ワクチンは「予防接種法」に基づき、市町村が実施する「定期接種」となりました。定期接種の対象者は、生年月日により毎年異なりますのでご注意ください。対象期間内に市町村の契約医療機関や保健所で接種を受けると「公費の助成」が受けられますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
接種間隔は5年以上
肺炎球菌ワクチンは、インフルエンザワクチンと異なり、5年以上の間隔で接種することが推奨されています。これは、5年以内に再接種する必要がないことと、注射部位の痛みが強くなる可能性があるためです。
インフルエンザワクチン
との同時接種
肺炎の予防効果を高めるために、インフルエンザワクチンとの同時接種が推奨されています。
帯状疱疹ワクチン
 帯状疱疹は80歳頃までに、3人に1人が発症するといわれています。
帯状疱疹は80歳頃までに、3人に1人が発症するといわれています。
50歳以上で水痘にかかったことのある方は、帯状疱疹予防ワクチン(水痘ワクチン)を接種することができます。
当院では2種類のワクチン(水痘ワクチン、シングリックス)をご用意しております。
台東区に住民票のある満50歳以上の方は接種費用の一部が助成されます。
2025年4月より65歳以上の方は定期接種の適応となり、接種費用が助成されます。
| 水痘ワクチン | シングリックス | |
|---|---|---|
| ワクチンの種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
| 接種回数 | 1回 | 2回(2ヶ月あけて二回目) |
| 予防効果 | 50~60% | 90% |
| 持続期間 | 5年くらい | 9年以上 |
| 副作用 | 接種部位の腫れや痛み (皮下注射) |
接種部位の腫れや痛み (筋肉注射なので痛みの頻度多) |
| 料金 | 8,800円(税込) *台東区助成利用で自己負担4000円 |
22,000円(税込)/回 *台東区助成利用で自己負担11000円 |
| 長所 | 1回ですむ、値段が安い | 予防効果と効果持続が長い |
| 短所 | 免疫低下者には生ワクチン なのでうてない |
当院では、ワクチンの効果持続時間や予防効果を考慮し、シングリックス(不活化ワクチン)を採用しております。
シングリックスワクチンをご希望の方はWeb予約からお申し込みをお願い致します。
なお、一度お申し込みいただいたワクチンは、メーカーに発注いたしますので、以後のキャンセルはできません。
お申し込み後、接種されなかった場合でもキャンセル料金(17000円)を請求させていただきます。ご了承ください
接種できない方
- 免疫異常のある方(悪性腫瘍、白血病、HIV感染など)
- 免疫抑制剤を使用している方
A型肝炎ワクチン
A型肝炎は、A型肝炎ウイルス(HAV)の感染によって起こる肝炎です。
A型肝炎ウイルスはヒトや動物の糞便中に存在し、ウイルスに汚染された手などから口を通じて感染します。感染者は発症前から糞便中にウイルスを排出するため、気づかないうちに他の人への感染源となることがあります。
感染力は強く、気づかないうちに軽症で済むこともありますが、劇症肝炎を発症することもあります。日本では自然感染の機会が少なく、ほとんどの日本人が免疫を持っていないため、ワクチン接種によって感染のリスクを減らすことが重要です。
ワクチンは1歳以上で2~4週間の間隔をあけて2回接種し、初回接種から約6か月後に追加接種します。小児だけでなく成人も接種可能です。
B型肝炎ワクチン
B型肝炎ウイルスは、特に乳幼児期に感染すると、菌の排除が難しくなり、菌を保有し続けやすくなるウイルスです。肝硬変や肝臓がんに発展することもあります。
感染予防策のひとつにワクチン接種があります。大人になってから接種するよりも、小児期に接種した方が抗体を獲得しやすいことがわかっています。
お子さまの体を守るためにも、B型肝炎ワクチンの接種をおすすめします。
平成28年(2016年)10月(2016年4月1日以降お生まれの方)より、生後2ヶ月から1歳までの定期接種となりました。公費接種の対象年齢を過ぎていても、自費で受けることができますので、ご相談ください。
- 定期接種:1歳までに3回接種
- 自費接種:3回接種
麻疹風疹ワクチン
麻疹ウイルスとは
麻疹は麻疹ウイルスによって引き起こされる感染症で、一般的には「はしか」と呼ばれます。感染経路は、空気感染・飛沫感染・接触感染です。その感染力はきわめて強く、免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%が発症します。そのため小児だけではなく、大人も注意が必要です。
通常38℃程度の発熱やかぜ症状がはじまります。2~4日発熱が続いたあと、39℃以上の高熱と上記のような発疹が出てきます。また発疹が出る前に頬の粘膜に「コプリック斑」という白い斑点を認めることもあります。通常は7日~10日で回復しますが、免疫力の回復には1か月程度必要です。
さらに注意が必要なのが合併症で、肺炎や中耳炎、脳炎などを合併することがあり、分注意する必要があります。また、麻疹にかかった人は数千人に一人の割合で死亡することがあります。近年、新型コロナの流行がおさまるとともに麻疹報告例が増えてきています。なので、昨今麻しんに対しても予防接種が注目を集めています。
風疹ウイルスとは
風疹とは、風疹ウイルスによる感染症で、一般的に「三日はしか」と呼ばれることもあります。麻疹と同じく春先から初夏にかけて多く発生し、飛沫感染や接触感染が主な感染経路です。
2012年~2013年に20~40代の男性を中心に全国で大規模発生が見られており、予防接種を受けていない方や風疹に罹ったない方などは流行に注意が必要です。風疹は、約2週間の潜伏期間の後、発熱や首の後ろのリンパ節の腫れを認めます。発熱は半分に見られる程度です。その後、顔面から始まり、2~3日で体幹・四肢に拡大するような発疹が出てきます。通常3~5日でなくなります。基本的に予後は良好であり、感染しても明らかな症状がでることがない(不顕性感染)人が15%から30%程度います。そして一度感染し治癒すると、大部分の人は終生免疫を獲得します
- 特に大人で感染すると、関節炎や急性脳炎などの合併症発症する可能性があります。
- また妊娠初期に母親が風疹に感染すると、胎児に風疹胎児症候群を引き起こす可能性があります。これは、聴覚障害、視覚障害、心臓の欠陥、精神遅滞などの先天的な障害を引き起こす可能性がある状態です。そのため、妊婦さんとそのパートナーの予防は特に重要です。
-
麻疹風疹ワクチン
- 麻疹ワクチンも風疹ワクチンも1回の接種で95%の確率で免疫を獲得できるとされています。2回接種すると免疫獲得率はさらに向上し、麻しん・風しん両方に対し97%以上とされています。回数は1回接種でも十分ですが、2回接種時には通常4週間をあけて接種します。しかし、接種を受けた人全体の中で接種完了(2回接種)の割合が低いと、国外からの輸入感染による集団発生のリスクが残ります。
そのため、国民全員が最低でも1回以上、できれば2回の予防接種を行い、集団免疫を高めることが大切です。
特に30歳代後半から50歳代の男性は風しんに対する免疫が不足またはない場合が多く、抗体価の確認もしくはワクチン接種が勧められています。自費診療での血液検査・ワクチン接種を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
血液検査・ワクチン費用
風疹IgG(血液検査) 4400円
麻疹IgG(血液検査) 4400円
麻疹風疹ワクチン(MRワクチン) 11000円